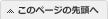Top > 工学系のご案内 > 学科・専攻等の紹介 > 国際開発工学専攻
国際開発工学専攻 Department of International Development Engineering
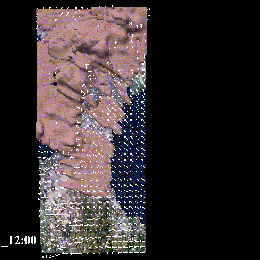
マニラの交通大気汚染の数値シミュレーション
国際開発工学専攻は、人類の福祉の向上を工学的側面から支えるための教育研究を行うことを目的として、1999年4月に設置された専攻である。この目的のためには、基礎的な生活水準が得られていない開発途上国の実効的で効率的な開発を担うことのできる教育研究を進めていく必要がある。また、人類に大きく影響する環境問題などの諸問題が、国際的で広い工学的分野に関係している。例えば、地球温暖化の問題では、ある一国での二酸化炭素放出が、世界中に影響を与える。そして、この問題を解決するためには、化工、機械、電気・情報、土木等の技術を駆使して、現実的で低コストな方法を探らなくてはいけない。また、開発途上国に対しても、そのような技術を移転していかなければ、問題を解決することはできない。これらの諸問題の解答を導き出すために、本専攻では一つの工学分野だけでなく、化工、機械、電気・情報、土木系および社会科学系の専門を持つ教員が協力し、総合的研究体制を形成している。さらには、国際協力機構等とも連係して、国際協力の場で必要となる地域環境・国際経済などの教育研究を積極的に行っている。日本国憲法前文にあるように、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって」、しかも、そうでなければこれからの問題を解決することはできないのである。
本専攻の教育における最大の目的は、国際的な枠組みの中で問題を解決していくことができる能力、勇気、リーダーシップを持った人材を育成することであり、そのためのカリキュラムを用意している。既存の分野と国境の垣根を越えたネットワークを持つ専門家であることが、これからのエンジニアには求められている。
講座・分野
- 国際環境講座
- 開発プロジェクト分野
- 開発環境分野
- 開発アセスメント分野(連携)
- 開発基盤工学講座
- 地域基盤分野
- 電気情報基礎分野
- 開発産業システム講座
- 開発資源分野
- 生産システム分野
- 国際共存講座(協力)
- 国際共存分野
主な授業科目
- 国際開発プロジェクト特論
- 国際環境工学
- 開発プロジェクト演習
- International Development Projects with Case Method
- Sustainable Development and Integrated Management Approach
- Applied Economics for Engineers
- Project Evaluation for Sustainable Infrastructure
- Mathematical Science in Development Engineering
- 国際共存
- Engineering/Science and Society
- 国際実習演習A/B
- Evaluation and Planning of Regional Infrastructure
- Advanced Geotechnical Engineering
- Regional Atmospheric Environment
- Durability and Maintenance of Construction Materials
- Advanced Concrete Technology
- Fundamentals in Electrical Engineering
- Rural Telecommunications
- Basic Theories for Information Processing
- 国際資源産業論Ⅰ.Ⅱ
- 開発プロセスシステム論
- 国際開発生産システム工学
- 開発シミュレーション工学
- 国際開発工学特別実験
- 国際開発工学講究